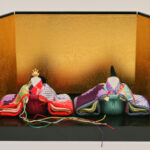ちりめん細工・白鳥袋
冬になるとシベリアあたりからやって来た白鳥が、凍てつくような北の湖で越冬する姿は、実に美しいものです。
この作品はアンデルセンの「みにくいアヒルの子」からヒントを得たものです。
アヒルのひなに混じった白鳥のひなは、余りにも違う姿にいじめられてしまいますが、成長になって自分が美しい白鳥であったと気付いた時には、どんな気持だったでしょうか。
人や物は外見だけで見てはならない、そんなことを作者は伝えたかったのだと思います。
それにしても実に美しい姿の、創作白鳥袋が出来上がったものです。
ちりめん細工,e-ちりめん優遊館 公式Facebookページ
ちりめん細工,e-ちりめん優遊館


楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・松かさ袋
「まつかさ」(まつぼっくり、松ぼくり)を模した作品です。古作にも多く見受けることができます。
まつかさの鱗片を四角形で作り、下向きに下がる三角のヒダの部分を鱗片の先端に見立てた姿は、開いた状態のまつかさの特徴を実にうまく捉えています。
いつも申しあげているように、ちりめん細工古作を最初に考え出した人は、その観察力と作品に写すアイデアを見事にマッチさせています。
一つの作品を作り出すことは私が考えている以上に、物を見る目から始まって、それをいかにうまく作品に取り入れるかという智恵と技術が必要で、たいへんな作業の課程を経ることが必要なのかもしれません。
大きさも大小まちまちで実用、お飾りにもぴったり。派手な色合いからシックな彩のものまで、見た目も楽しませてくれる松かさ袋です。
ちりめん細工,e-ちりめん優遊館 公式Facebookページ
ちりめん細工,e-ちりめん優遊館


楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・みみずく袋
みみずく袋はまつかさ袋を元にアレンジした作品です。胸の襞の部分を見ると、まつかさ袋そのままの姿です。
ミミズクよりはフクロウのほうが一般的で、ふくろう袋にしてもいいと思うのですが、そこは作者の拘りと言うもの。
ミミズクはフクロウの仲間の中で耳のような羽角を持つものの総称です。
この袋にもちょこんとした耳(羽角)を付けて、フクロウとは一線を画した姿に作り上げています。
良く見ていると確かに羽角のない頭は、何やらのっぺらぼうで締まりがありません。
最初に考えて作った作者は既に他界されて、その意図を聞くことが出来ませんでした。
しかしこの方の鋭い観察眼と物作りへの拘りから考えると、やっぱり最初から羽角のあるミミズクにしたかったような気がしてなりません。
ちりめん細工,e-ちりめん優遊館 公式Facebookページ
ちりめん細工,e-ちりめん優遊館


楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・糸菊袋
秋も深まりあちらこちらから菊の話題も聞こえてくる季節になりました。
菊の花言葉は「高貴」。もちろん天皇家の家紋にも使われている、日本を代表する花の一つです。
菊は、江戸時代より栽培が流行し始め、現在に至るまで品種の改良と共に、その鉢植えの見事さを競う愛好家が多いことでも群を抜いています。
この袋は「糸菊袋」と名づけましたが、愛好家の人々の間では「管物」(くだもの)といわれたり、また「乱菊」と呼ぶこともあると聞いています。
もっとも一般的には乱菊という言葉は着物などの文様のことで、菊の種類を表すものではなさそうですが。(どうでもいい話で失礼)
でも糸菊袋と呼ぶよりはむしろ「乱菊袋」と呼んだほうが、よりいっそうこの袋の雰囲気が伝わるかもしれません。
ただし「管物袋」と言ってしまうと、何やら果物の袋に思ってしまいそうですね。
いずれにしてもこの作品は丁寧なつくりと共に、細い管状の花弁のしなやかで優雅な姿を、余すところなく伝えてくれる作品です。
ちりめん細工,e-ちりめん優遊館 公式Facebookページ
ちりめん細工,e-ちりめん優遊館


楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・菊袋のつるし飾り
もうあちこちから菊の便りが聞こえてくる時期になってきました。
菊は古くから品種の改良が行われて、今では様々な形の花を楽しむことができます。
このつるし飾りの花は、昔からあるオーソドックスな形で、江戸時代に当時の菊を見ながら形を考えたものと思われます。
今の時期にお部屋のお飾にはピッタリで、お家の中にも潤いが生まれそうです。
ちりめん細工,e-ちりめん優遊館 公式Facebookページ
ちりめん細工,e-ちりめん優遊館


楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。