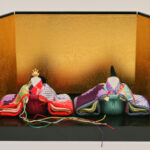ちりめん細工・押し絵の羽子板
年の瀬になりお正月も近づくと、ついついお正月にちなんだ作品をご紹介したくなります。
やはり羽子板といえばお正月にはつき物のようなものですから、鯛車や小槌などおめでたいものが押し絵で作ってあります。
かつてはお正月の遊具であったものですが、最近では羽子板で遊ぶ子供たちを見かけることもありません。
もっぱらお飾りとして使われているようで、東京浅草浅草寺の羽子板市などで販売されている物も、実用的遊具というより絢爛豪華で室内装飾品としての性格を持っています。
女の子のお守りとして羽子板が厄を跳ね飛ばすということで使われ始め、そしてこれも古来より受け継がれてきた慣習と日本文化の象徴的な遊具兼装飾物ということが出来ます。
http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/
松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。
http://e-chirimen.com/
楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。

2013年 十二支(干支) 巳
つい先日師走に入ったかと思っていたら、もう今日は12月8日。
この月だけは時間の経過スピードが、いつもより格段に速く感じてしまいます。
そしてまた、毎年恒例の十二支をご紹介する時期になりました。
来年の干支は「巳」。巳といえば蛇ですから、何となく難しそうなお顔がどのように出来るか、楽しみにしながらも少々心配でした。
出来上がってみると古典の基本を残しつつも、ちょっとお茶目で現代的な雰囲気を持ち合わせた作品が出来上がりました。
もっとも毎度のごとく制作までのご苦労は私には分からないものの、随分な時間をかけて考えたに違いありません。
ところで頭の飾りになっている組紐の結び方はつゆ結びと言い、別名「蛇結び」、英語ではSnake Knotとも呼ばれているようです。
一説によると蛇の鱗に見えるので、こういう呼称もあるということですが、確かなところは分かりません。
こんなところにも作ることも出来ない講釈専門の人間が、文章のネタを考えやすいような配慮がなされていて、講釈師にとってはまことにありがたい限りです。
最も作者はそんなことを考えて、この作品を作ってくれたかどうかは全く定かではありませんが…..。
http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/
松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。
http://e-chirimen.com/
楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。

ちりめん細工・舞い猿
とうとう今日から師走。師(先生)も忙しくて走り回るということですから、世の奥様方もお忙しいに違いありません。
ちりめん細工の舞い猿は、神楽を舞っている猿を模した作品で、古作の中にも見ることが出来ます。
高貴な雰囲気の中にもユーモラスなしぐさは、見ていてなんとも楽しい作品です。
むかし子供のころに見た猿回しの装束も、かなり厳かな雰囲気のものが多かったのを覚えています。
何となく猿の顔と装束がアンバランスで、それがまた面白さをかもし出していたのかもしれません。
そもそも猿と人間の付き合いは、災いが去るというところから、厄除け、家内安全を願う動物の象徴だったようです。
http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/
松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。
http://e-chirimen.com/
松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・創作押し絵の巾着
これは果たして「巾着」と言っていいのでしょうか。
五角形の窓の開いた枠があって、内側に円筒状の物を入れる部分が付いています。
その円筒部には浮世絵風の押し絵が施され、その部分はくるくる回るようになっていて、どこからでも押し絵が見えるようになっています。
確か古作の中でもこのような作品を見たことがあるようなのですが、全く同じような仕組みではなかったような気がします。
そして底を見てみると…..。

ちりめん細工・創作押し絵の巾着
何と底にも押し絵があり、円筒が上げ底のようになっている凝りよう。
アイデアもさることながら、とにかく作品作りに全身全霊を傾けられた力作だと思われます。
作者のご努力には心より敬意を表します。
http://e-chirimen.com/
楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。
http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/
松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・掻巻き人形袋
晩秋ともなると季節は正直なもので、特に朝晩はめっきり冷え込む日が多くなってきました。
こういう季節になるとやっぱり暖かそうな掻巻きにくるまった、掻巻き人形袋をご紹介したくなります。
この「掻巻き」とういう寝具を、実際にご存知の方も少なくなってしまったかと思いますが、私の母方の祖父はこれを一時期愛用していたのを覚えています。
袖に手を入れて肩まですっぽりかぶることの出来る掻巻きは、実に暖かそうに見えました。
もしかすると今の時代にも、羽毛版掻巻きなどがあるかも知れません。あれば使ってみたいですね。
この作品もまた写真にするには結構難しく、お顔が隠れてしまったりすると、せっかくの作品が台無しになってしまいます。
といって、顔が上に向いていたりするといかにも不自然な感じがしますから、少しだけでも横を向いていてくれると、たいへんありがたいのですが…..。
作者の苦労を知らない講釈師は、またまた適当なことを言ってしまいます。
ごめんなさい。
http://e-chirimen.com/
楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。
http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/
松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。