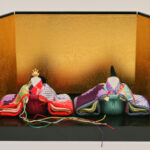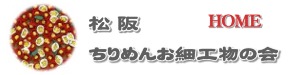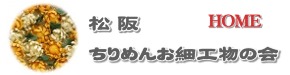ちりめん細工・椿の編み籠巾着
高さが20cmほどの実用的な大きさの巾着です。
編み籠(籠底)の上には六角つなぎの技法を生かした、今の時期にはぴったりの椿の文様がちりばめられています。
椿の花びらの数が6枚ということはありませんが、いかにも椿の花を連想させる形になっていて、作者の着眼点のセンスをうかがわせています。
そもそも私などはこのちりめん細工に出会うまで、ツバキかサザンカ(寒椿)かの見分けも付かない男でしたが、25年以上もちりめん細工の世界に寄り添っているうちに、今では区別も付くようになりました。
草花や四季折々の行事や自然の事象など、ちりめん細工の世界は日本の季節の移り変わりが持つメリハリを、強く反映した手芸だと言えましょう。

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。
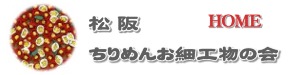
松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・切りばめ細工の巾着
一見中央の文様はアップリケをしたように見えるます。実はこれ、布を文様の通りカットして、その形の中に縫い込んで作られています。
古作の中にはこの「切りばめ」の技法を使った作品を、数多く見ることができます。
最初に切りばめの作品に出会ったのは鶴亀に松の文様で、その巧妙なできばえからは、染で柄を作り出したものだと思い込みました。
しかし近くに寄ってよく見ると、何と、染ではなくて布をはめ込んで作ってあるではありませんか!これにはまったく驚いた記憶がよみがえってきます。
最近では余り見かけなくなった技法ですが、技術的にも難しい面がある以上に、私には想像できない根気のいる作業も必要なのでしょう。
ちりめん細工の世界は、いつまでたっても驚きが絶えることはありません。

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。
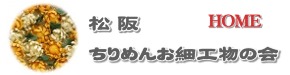
松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・みみづく袋
ミミヅク(ミミズク)とはフクロウ科の中でも、羽角(うかく、耳のように見える部分)があるものの総称だとのこと。
よく見ればこのみみづく袋にも、かわいらしい耳が付いています。
私なら「ふくろう袋」と名づけてしまいそうなところを、ちりめん細工を極めた人の頭脳では名前にもこだわって、「一ひねり」したかったのでは。と、勝手な想像をしています。
よく見るとボディーの部分はまつかさ袋をヒントにヒダが下がっていて、いかにもミミヅクらしさ?を演出しているようです。
すこし大きめに作らた頭とまん丸で優しそうな目は、猛禽類の鋭さを可愛らしさに変貌させているのもさすがというほかありません。
ちりめん細工作品はほかの作品がヒントになっていたり、またその技法を取り入れて新しいものを創造していくところにも、見る者にとっても大きな楽しみを提供してくれます。

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。
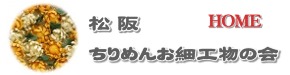
松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・籠底の創作巾着
籠底になった実用的な大きさの巾着です。
口べりの下側は四角になった形の中に、七宝袋のように少し緩みを持たせた布で十文字のデザインが施されています。
そして少し籠底の部分に垂れたひだは、何となく松かさ袋を思い出します、
いろいろな技法やデザインをヒントに、ご自分でアレンジした作品だと思っていますが、私などが講釈を言っているよりもはるかにアイデアと技術が必要だったのでしょう。
もうすぐ七五三。お孫様のお参りにもピッタリの巾着ではないでしょうか。

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。
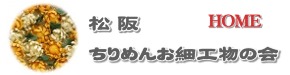
松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・糸菊袋
秋も深まりあちらこちらから菊の話題も聞こえてくる季節になりました。
菊の花言葉は「高貴」。もちろん天皇家の家紋にも使われている、日本を代表する花の一つです。
菊は、江戸時代より栽培が流行し始め、現在に至るまで品種の改良と共に、その鉢植えの見事さを競う愛好家が多いことでも群を抜いています。
この袋は「糸菊袋」と名づけましたが、愛好家の人々の間では「管物」(くだもの)といわれたり、また「乱菊」と呼ぶこともあると聞いています。
もっとも一般的には乱菊という言葉は着物などの文様のことで、菊の種類を表すものではなさそうですが。(どうでもいい話で失礼)
でも糸菊袋と呼ぶよりはむしろ「乱菊袋」と呼んだほうが、よりいっそうこの袋の雰囲気が伝わるかもしれません。
ただし「管物袋」と言ってしまうと、何やら果物の袋に思ってしまいそうですね。
いずれにしてもこの作品は丁寧なつくりと共に、細い管状の花弁のしなやかで優雅な姿を、余すところなく伝えてくれる作品です。

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。
ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。
ホームページにもぜひお立ち寄りください。
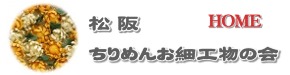
松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。
会員の作品もたくさんご紹介しています。